

バナナから経済社会を読み解く
果物の中でも身近で親しみのある存在のバナナ。いつ、どこから、どのようにして、私たちの食卓に届くようになったのでしょうか。その仕組みを探ると、日本やフィリピン、南米、そして世界の経済社会の構造が自然と浮かび上がってきます。
バナナを通じて社会や経済の仕組みを知る
『バナナと日本人―フィリピン農園と食卓のあいだ』著・鶴見良行(岩波新書、1982年)
「バナナ栽培こそが人類最初の農業だ」という説があるそうですが、日本では、日露戦争の直前にほんの少し台湾から輸入されるようになりました。それから徐々に日本人に受け入れられるようになり、戦後には台湾バナナブームが起きるほど多くの人が好む果物になりました。しかし、1970年代からは、台湾のバナナはフィリピンのバナナにあっという間に取って代わられます。
いま街のスーパーマーケットでは、主にフィリピンや南米のバナナが多く並んでいますが、品種、植生、栽培法などの農学的条件から、生産地、消費地のそれぞれの気候や流通、土地所有の形態、産業組織(寡占状態)、経済社会的要因に至るまで、様々な要因が凝縮されて、私たちは目の前のバナナを手にしています。その中で著者の最も主要なメッセージは、いまバナナを作っている人々は、自らは食べたくもないバナナを、非自然な状態の中で栽培しているということ。その現実を私たちは知らなければならないということです。
今流に言えば、ブラック企業と分かっていても、私たちはその企業のサービスを利用し続けざるを得ない現実があり、それが現代の社会システムといえます。仮に私たちがバナナを食べることを止めたとしても、あるいはもっと多くのバナナを買ったとしても、そしてなにより著者が主張しているように、消費者が生産者にもっと思いを寄せたとしても、本書に描かれたバナナ生産に携わる人々の悲しい現実は、簡単に解決されることはないでしょう。
私たちは、ただ単に安くて美味しくて安全なものを求めているに過ぎないわけですが、より良い食を求めるという素朴な行為が、実は複雑で意図しない社会的意味をもってしまうことを本書は改めて問いかけています。
他にもこんな記事がよまれています!
-
Column

2023.09.25
学生の共食の実態から見たアフターコロナの変化と食
立命館大学食マネジメント学部
小沢 道紀 -
Interview

2019.04.01
惣菜サービスが企業を救う! 「オフィスおかん」が勝ち続ける理由
株式会社おかん
沢木 恵太 -
Interview

2018.04.09
チョコで人を幸せに。ポッキーブランドマネージャーの仕事って?
江崎グリコ株式会社
田中 国男 -
Interview

2023.07.04
ポートランドに学ぶ、食を通した地域経済とコミュニティの活性化
エコトラスト
エマ・シャラー -
Interview
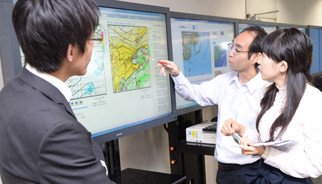
2019.04.15
全産業の1/3が改善!? 日本気象協会が提唱する「食の天気予報」
一般財団法人日本気象協会
中野 俊夫 -
Column

2018.07.03
おにぎり1個、食パン1枚はNG? 理想の朝食メニューを考える
立命館大学食マネジメント学部
保井 智香子