

駅ナカ「食」のおみやげ事情から見た地域創生
金沢駅など一昨年開業した北陸新幹線の駅だけでなく、東海道・山陽新幹線の各駅はリニューアルが進み、構内にある売店施設と販売されているおみやげの充実ぶりには目を見張るものがあります。また、道の駅や高速道路のサービスエリアも多くの立ち寄り客でにぎわいを見せており、その土地ならではの、そこでしか買えない「食」のおみやげが主役になっています。なぜ、これほどまでに「食」のおみやげが増えているのでしょうか。それは、おみやげを求める「旅行者」とおみやげを供給する「地域」の双方のニーズがうまく合致したからと言えそうです。
profile
-
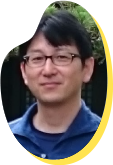
-
株式会社地域計画建築研究所
高田 剛司(たかだ たけし)
専門は、観光まちづくり、地域・産業振興。まちづくりのコンサルタントとして自治体の調査・計画づくりに携わるほか、商店街や集落等において、地域の人々によるビジョンづくりやプロジェクト運営のコーディネーター役として活動している。訪問先で、その土地の食材を使った料理を食べることが何よりの楽しみ。好きな食べものは、うなぎ。
その土地の食材でできたおみやげを買いたい「旅行者」
パソコンやスマートフォンが普及し、今日では、全国各地の食べ物を自宅で簡単に取り寄せできるようになりました。それにも関わらず、旅行あるいは出張に行った際に人々がおみやげを買い求める習慣は、今も昔も変わりません。むしろ、他の人が買っていないものや話題性のあるものを求めて、以前よりも「その土地ならでは」のプレミアム感を重視しておみやげを買う傾向が一層強くなっている気がします。チョコレート菓子やスナック菓子などを製造する大手製菓メーカーも、こぞって「ご当地限定」のおみやげを開発し、商戦を繰り広げています。
また、フェイスブックやインスタグラムといったSNSの普及により、ユニークで珍しいおみやげを購入し、画像をアップすることで、他の人に自慢したい、驚かれたいという旅行者の心理が働いている一面もあるでしょう。
食のおみやげづくりを通じて経済を活性化させたい「地域」
一方、人口減少社会に突入した日本では、特に地方のまちにおいて、交流人口を増やすための地域間競争が始まっています。というのも、交流人口の増加を通じて、地元の商品を買ってもらい、地域経済の発展や一次産業の振興に結び付けたいという期待があるからです。その土地ならではの食材を利用して6次産業化(1次産業+2次産業+3次産業)に取り組むことで、まちの農水産業や商工業の活性化につながるため、農水産物を利用したおみやげの開発が民間事業者だけでなく、商工会議所・商工会など地元の経済団体や行政も先頭に立って盛んに取り組まれるようになってきています。
その地域の「土」から「産」まれた「食」のおみやげ
「おみやげ」の言葉の由来は諸説あるようですが、漢字表記の「お土産」については、文字通り「その土地の産物」という意味になります。食の観点から見れば、その地域の「土」からできた農作物を使い、商品を製造(生産)するわけで、「おみやげ(お土産)」は地域性をアピールするためにうってつけのツールといえるでしょう。そのようにして見てみると、駅ナカでたくさん見かけるようになった「食」のおみやげから、地域創生にかけるそのまちの意気込みが伝わってくる気がします。
他にもこんな記事がよまれています!
-
Interview

2018.09.11
食や地域と密接につながる、住まいづくりの仕事
伊藤忠都市開発株式会社
-
Column

2019.06.20
外食チェーン店での食事を「会計脳」で考えてみよう
立命館大学食マネジメント学部
酒井 絢美 -
Interview
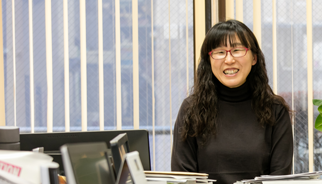
2017.04.10
料理雑誌・編集長が語る、食業界の「作り手」と「伝え手」の思い
株式会社料理通信
君島 佐和子 -
Interview

2023.02.07
よこすかポートマーケットがめざす、フードエクスペリエンス
よこすかポートマーケット運営管理室
子安 大輔 -
Interview

2017.05.17
「おやつ」から「嗜好品」へ。明治 THE Chocolateが変える日本の食文化
株式会社明治
山下 舞子 -
Column

2021.03.26
旅と食。反芻される思い出
立命館大学食マネジメント学部
加部 勇一郎