

毎日の食事が一層おいしくなる「おいしさの法則」
私たち生物は生きるために「食べる」という行為を行いますが、「おいしく食べる」という食を楽しむ行為は、人間特有のものです。とはいえ、せわしない現代社会では食事を簡便に済ませてしまうという人も多いのではないでしょうか。ここでは、毎日の食事をよりおいしく楽しむための「おいしさの法則」を紹介します。
profile
-
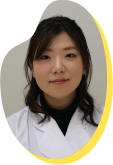
-
立命館大学食マネジメント学部 助教
本田 智巳(ほんだ ともみ)
専門は食物学、調理科学。農産物の抗酸化特性に関する研究や、産官学連携による特産物や未利用農産物を使用したレシピ・加工品等の開発に従事。現在は、若年層への健康的な食生活と地産地消の推進のため、SNSを活用した食育啓発に取り組んでいる。好きな食べ物はスイカ。
味だけじゃない? 「おいしさ」を構成する要因とは
食事をして「おいしい」と感じる時、食べ物の味だけではなくさまざまな要因が関与しています。これは、私たちが「おいしさ」を味覚・視覚・聴覚・嗅覚・触覚の五感で感じているためです。食べ物の「おいしさ」を構成する要因には、味や香りといった化学的要因と、色や形、温度やテクスチャー、咀嚼音などの物理的要因があります。
「おいしさの法則」おいしく食べるために味よりも重要なもの
では、さまざまな要因の中で特に「おいしさ」に関与するものは何なのでしょうか。「食べる」という行為は食べ物を口にするものですので「味」が最も重要かというと、実はそうではありません。私たちが食べ物を食べて「おいしい」と感じる時、先ほど挙げた五感の中で「味覚」からの情報は1%程度に過ぎず、80%以上を「視覚」からの情報で判断しています。つまり、「おいしく食べる」ためには、食べ物を口にする前に「おいしそう」「食べたい」と感じるような「外観」がとても重要なのです。
「おいしく魅せる」ためには
みなさんはどんな食べ物をみると、「おいしそう」「食べたい」と感じるでしょうか? 彩りや焼き色、てり・つや、切り方、盛り付けの仕方など、「おいしく魅せる」ための要素はいくつもあります。例えば、この中で彩りを意識してみてください。旬のものを中心に赤や黄、緑、紫、茶、白などの食材を組み合わせると、料理がぐっと華やかになる上、栄養バランスもよくなります。
また、野菜を輪切りや千切りだけでなく、ピーラーを使って薄くリボン状に切ってみるなど、いろいろな切り方をして変化をつけてみるのもよいでしょう。器に盛る際も、平らによそうより真ん中を少し高く整える、仕上げに小ねぎや胡麻を散らすというひと手間で、見映えに差が出ます。
忙しくても毎日の食事を楽しむコツ
とはいっても、忙しい日々の中で食事は出来合いのお弁当やお惣菜で済ませてしまうなんてこともありますよね。でもそんな時、「おいしいはずなのに、なんだか味気ないな…」と感じたことはありませんか? 買ってきたお弁当やお惣菜も、パックでそのまま食べるよりお皿に盛り付けるだけで見映えがよくなっておいしさが増しますし、お皿に移すのは片付けが面倒だという人は、食卓や周りの風景を心地よい環境にして食空間を整えてみるのもよいでしょう。
おいしい食事は心を満たしてくれますし、それによって充実感や幸福感を得られます。みなさんの毎日の食事がよりおいしく楽しいものになるよう、ぜひ「おいしさの法則」を意識して、目にもおいしい食事づくりを実践してみてください。
他にもこんな記事がよまれています!
-
Column

2018.07.03
おにぎり1個、食パン1枚はNG? 理想の朝食メニューを考える
立命館大学食マネジメント学部
保井 智香子 -
Column

2018.10.30
インドネシアのハラール認証最新事情(前編)
立命館大学食マネジメント学部
阿良田 麻里子 -
Interview

2019.02.13
脱ステレオタイプ! 個の時代をゆくエナジードリンクの新定義
サントリー食品インターナショナル株式会社
脇 奈津子 -
Column

2019.10.07
「おふくろの味」はどんな味?
立命館大学食マネジメント学部
鎌谷 かおる -
Interview

2020.02.18
日本初のフードインキュベーター「OSAKA FOOD LAB」の挑戦
株式会社Office musubi
鈴木 裕子 -
Interview

2017.07.12
「食材ピクトグラム」で誰もが同じテーブルを囲める世の中へ
株式会社フードピクト
菊池 信孝